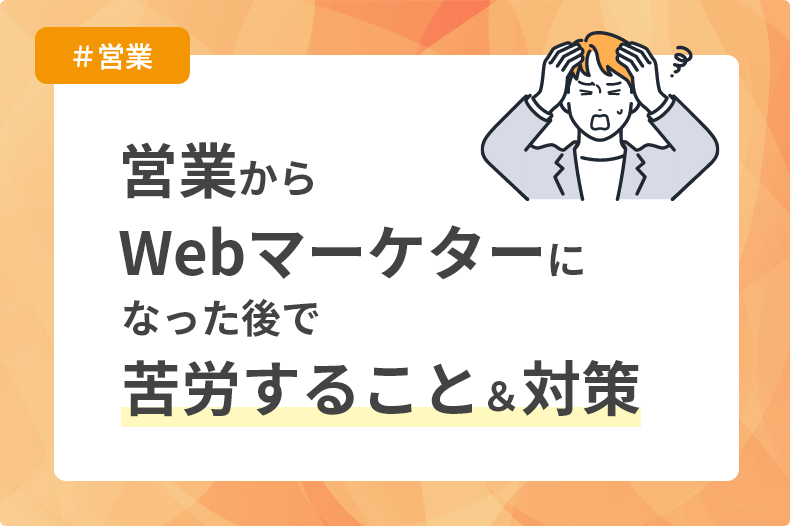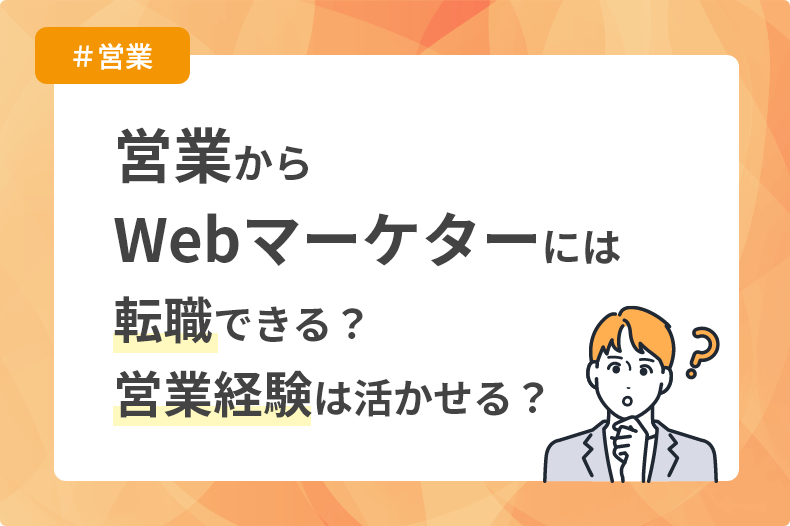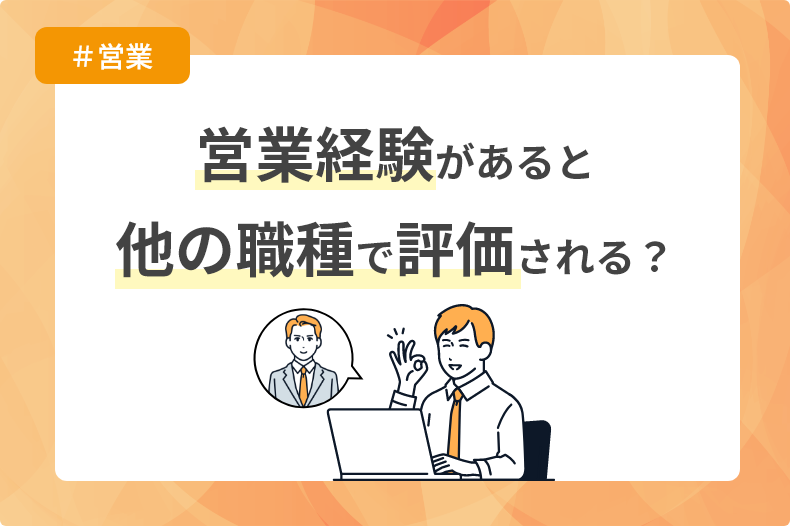新しいことにチャレンジしたい元営業にWebマーケターは合う?
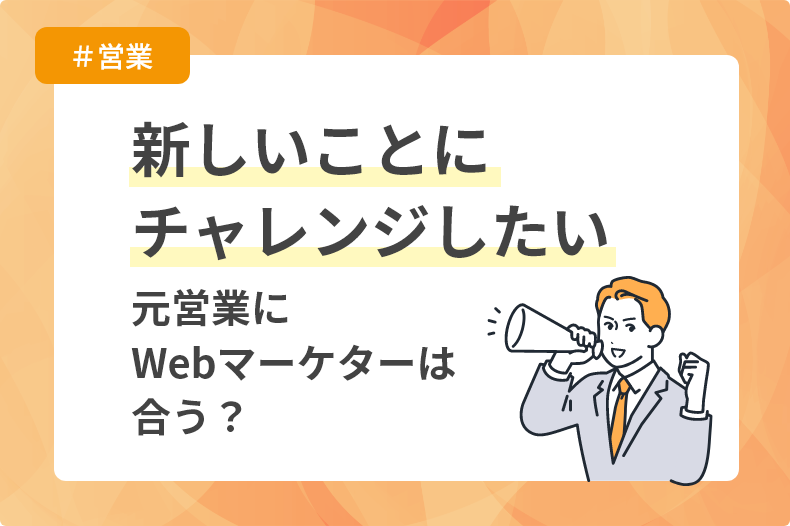
営業職からの新たな挑戦シリーズ第1弾。
今回は、「新しいことをやりたい。だから営業をやめる」というテーマでお送りします。
世の中にはいろんなタイプの人がいますよね。
ひとつのことを長く取り組みたい継続型タイプもいれば、常に新しいことをしていたい冒険型タイプの方もいます。
また、継続型タイプの人であっても、ある時にふと「飽きた」と思うこともあります。
ずっと営業に情熱を燃やしていたはずなのに、興味を持てなくなってしまったら…
やれてはいるけど、腰が重くて苦痛。新しいことがしたい…
そんな方に、Webマーケターという仕事は合うのでしょうか?
目次
飽きるとは、人類生存繁栄のためのメカニズム?
飽きるとは、同じ刺激を繰り返し受けることで慣れてしまう現象です。
これは人類が多種多様な場所に拡散し、発展していった原動力であるという説があります。
例えば、全員が同じ場所で過ごしている環境で自然災害が発生したらどうなるでしょうか?
巻き込まれて全滅する可能性も考えられますね。
皆がずっと同じ場所で同じ生き方をしていたら、何かあれば絶滅してしまいます。
飽きるとは、人類の根源が持つ生存戦略であると言えます。
対して、農耕による土地への定着により、発展した歴史もあります。
そのように、刺激を求め新たな開拓をする人、飽きに強く定着して繰り返す生き方をする人、その両方が居るから社会は成り立っていると言えるでしょう。

飽きが生じるパターン
人により程度差はあれども、何事も飽きるときは飽きます。
趣味や食べ物、仕事だってそう。
営業の仕事に飽きてしまう瞬間は、こんな状態になった時に訪れます。
- 新しい刺激がない。成長できない。
- 自分にとって簡単すぎる。
- 未来が見えてしまった。
それぞれ順に見ていきましょう。
新しい刺激がない。成長できない。

人には学習能力が備わっています。
だから同じことを繰り返していく中で、楽に、考えずに、自然に物事を処理できるようになっていきます。
入社したての頃、ポジションが変わった時、新しい仕事を任された時…
「最初」の頃は何もかもが新鮮で、新しい刺激をたくさん受けられます。
新しい刺激は、ワクワクや興奮を生みます。
しかし、経験によって繰り返し同じことをしていると、得られる刺激は減っていき、先が予想できるようになっていきます。
パターンに当てはめて作業的にクリアしていくと、考える必要がなくなり楽になる一方で、刺激は減少します。
そうなると、「つまらない」「飽きた」ということに繋がっていくのです。
常に新しい売りものが登場する職場なら、それをどう売るか考えるという刺激がありますが、1つのものを20年も30年も、ずっと扱っていく仕事も多くあります。
安定して同じものを売り続けられるという良い面もありますが、それが合わない人も居るということです。
簡単すぎる
営業が簡単すぎるというのは、スーパー営業パーソンの話かと思うかもしれませんが、そうとは限らず、身近に起こりえることです。
例えば、次のような営業のやり方に対して、簡単すぎると感じる場合があります。
- 決まった商品説明を繰り返す営業。
- 仕組みが出来上がっていて、型に沿って同じパターンで処理していく営業。
- 既存取引先を巡回しての、御用聞き営業。
人によっては、それが簡単すぎて「自分でなくても良いのではないか」とつまらなく感じてしまう場合があるようです。

経営サイドは、仕事を簡単にし、誰でもできるようにすることを求めています。
事業の持続性という観点から「属人化の排除」という経営テーマがあるからです。
そのおかげで個々の能力に依存せず、幅広く雇用を生み出せるわけですが、一部の人には物足りなく感じる場合があります。
また、給与・賞与の評価制度も、そのボリュームゾーンの人たちに合わせて組まれていることが多いものです。
結果、圧倒的に突き抜けた個の力を持つエースプレイヤーは、その組織の中で「貢献に対して評価がされない」と失望し、離脱することもしばしばです。
「自分の可能性を試したい」という転職も、この「簡単すぎる」が原因であることもあるのです。
未来が見えてしまった。

この先続けても自分はここ止まりだ、というものが見えてしまうと、今取り組んでいる仕事がつまらなくなってしまうことがあります。
一方で、先が予測できない状況というのは、新たな刺激に満ちています。
「自分はこの先どんな風になっていくのだろう、自分の未来はどんなだろう」
そう考えるとワクワクします。
結果、我慢してつまらないと感じている仕事を「仕事だから」と続けるか、またはその職場での仕事をやめて、新天地を求めるかの二択を迫られることになるでしょう。
Webマーケターの仕事ではどうか?飽きるか?
Webマーケターの仕事は、支援会社であれば様々な顧客のプロジェクトを、事業会社ならその事業をWebの世界を通して成功させることです。
そのためには、常に最新の知識や技術、情報を追う必要があります。
Webの世界では常に世の中の動向や技術、プラットフォームが進化していくので、5年前の知識が役に立たないということもしばしばあります。
昔の知識が通用しなくなった実例として、次のケースを紹介します。
SEO対策の方法
SEO対策として一昔前は正解だったことが、現在では完全にアウトなことがあります。
例えば、過去のSEO対策に「ページ内に検索キーワードをとにかく詰め込む」という方法がありました。
情報に直接関係のないワードがページ内にたくさんあれば、見る人は当然わずらわしさを感じます。
そこで、文字の色を背景と同化させて目立たせないようにしたり、サイズを限りなく小さくして隠したりする手法が流行した時期もありました。
昔はそんな裏技めいた方法で、検索エンジンでの上位表示が可能でした。
しかしこんな対策方法は、今では全く無意味な行為です。
時代は変わり、SEOで上位に表示されるコンテンツは情報として本質的に役立つものとなりました。
検索されそうなキーワードを詰め込んだものではなく、ユーザーにとって役に立つコンテンツが上位に表示されるようになったのです。
そのためSEO対策の方法も昔より高度になり、ユーザーの検索意図に沿った有益なコンテンツを考える必要があるのです。

Instagramの利用目的
かつてのInstagramは、視覚的に美しい写真や動画を投稿するプラットフォームでした。
2017年には流行語大賞に「インスタ映え」が選ばれ、インスタ映えを狙ったスポットや食べ物が登場し、その写真がたくさん投稿されていました。
しかし、最近ではInstagramの役割が「好き」を生んで「欲しい」を誘発する場に変化しています。
インフルエンサーが商品のリアルな使用感をレビューしていたり、「この春に行くべき都内のイベント3選」のように情報をまとめて紹介していたり、そんな投稿を見かけることがあると思います。
ここ5年程度で、「映え」から「新たな商品との出会い」を期待してInstagramを活用するようになったのです。

Webマーケターの仕事は、新しいことに挑戦したい人に向いている
Webマーケターが扱う商材には、BtoCもあればBtoBもあります。
全く知らない業界の仕事を支援することも日常です。
だからこそこれまで知る機会のなかった、世の中の裏側を知ることができる仕事でもあります。
刺激のない仕事は嫌だ。
自己成長に天井がある世界は嫌だ。
そんな風に新しいことをやりたいという営業出身の人にとって、Webマーケターはとても良い仕事だと言えるでしょう。